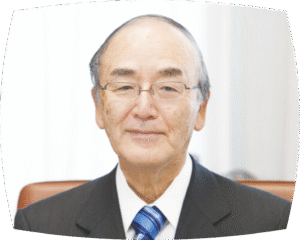
日本商工会議所名誉会頭
日本製鉄名誉会長
当法人顧問
三村明夫
Mimura Akio
……………………………………………………………
急激な職場の高齢化が進んでいます。特に人手不足が深刻な課題となってきた中小企業においては、シニア社員の方が健康を維持して、フレイルを予防し、いつまでもパフォーマンスを発揮して社会参加していただくことが、企業・個人・社会のために必須です。シニア社員の健康や、社員の未来にまで配慮できる企業姿勢は、時代に即した新たな企業価値でもあります。経営者、働く人双方の意識の向上と変革が求められています。それぞれの職場で、それぞれの地域で、さまざまな知見やインフラを活用しながら今日から取り組んでいただきたいと思います。
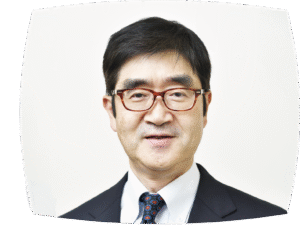
地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター理事長
東京大学名誉教授
東京大学附属病院元・副院長
日本老年医学会元・理事長
当法人理事
秋下雅弘
Akishita Masahiro
……………………………………………………………
年齢とともに体力・気力が低下した状態を「フレイル」といいます。フレイル自体は疾患ではないものの、これによって身体機能の低下や病気にかかりやすく、生活の質が低下する恐れがある状態です。平均寿命が延びているなかで、日常生活に制限なく生活できる健康寿命を阻害する要因といってよいでしょう。日本老年医学会が2014年に健康な状態と要介護状態の中間の状態を表す言葉として提唱し、医療機関や自治体などに普及しました。
実は50代の皆さんの約半数がフレイル相当の状態であるという調査もあるほど、「フレイル予防」はライフステージにおいてシニアの前段階であるミドル世代からの対策が必要です。ミドル世代は責任ある役職に就いたり、職場での立場が変わったり、プライベートも含めてライフステージが切り替わる時期です。また、さまざまな環境変化によるストレスを受けやすく、不摂生や運動不足なども相まって、健康診断で指摘される項目が増えていきます。しかし、働き世代でもあるので、出世や収入への影響を恐れて健康上の問題を言い出しにくく、体力や気力があるので無理もできてしまいます。ところが、このミドル世代の不健康・不適切な生活などの問題を先送りすれば、雪だるま式に健康上の問題は大きくなり、シニア世代にも響いてきます。フレイルは適切な対策次第で健康な状態に戻すことができます。50代であればまだ十分に加齢変化を止め、あるいは回復までも期待できる世代です。「まだ間に合う」という意味で、ぜひ50代からフレイル対策を早めに始めてほしいのです。なお、体調不良をおぼえる中高年期においては、病気の有無だけにとらわれることなくフレイルにも気に留めてほしいものです。こうした意識改革は、医師の私たちにも求められています。
フレイルは認知症とも関連しています。フレイルだと認知症になりやすく、進行も速く、また認知症の方にはフレイルの割合が高いのです。高齢化に伴って認知症の方がとても増えてきています。ご本人に対する医療や介護の負荷の大きさは言うまでもありませんが、介護のためにその下の世代が離職せざるをえないなど、社会全体に大きな影響が生じています。
口腔の健康も大切です。口はフレイルを予防するうえでさまざまな栄養を摂る器官として重要ですが、一方で口腔内細菌や歯周病菌が、肺炎や糖尿病などさまざまな病気を引き起こす場合もあります。
50代以降は、さまざまな病気が発症し、進行する年齢です。「疲れやすい」とか「気持ちが落ち込む」といったよくある訴えの裏に、がんなどの疾患が潜んでいることも少なくありません。「50代でまだ若いから大丈夫」「加齢してきたのだから仕方ない」などそのどちらも正しい考え方とはいえません。不安なことがあれば、迷わず早めに医療機関の門をたたいていただきたいのです。そのためにも、自分の大切な後半人生を守るためにも、ミドル・シニア期以降の健康リスクについて基礎的な知識を学んでいただき、「まだ間に合う」という意識をすべての方に持っていただきたいと思っています。
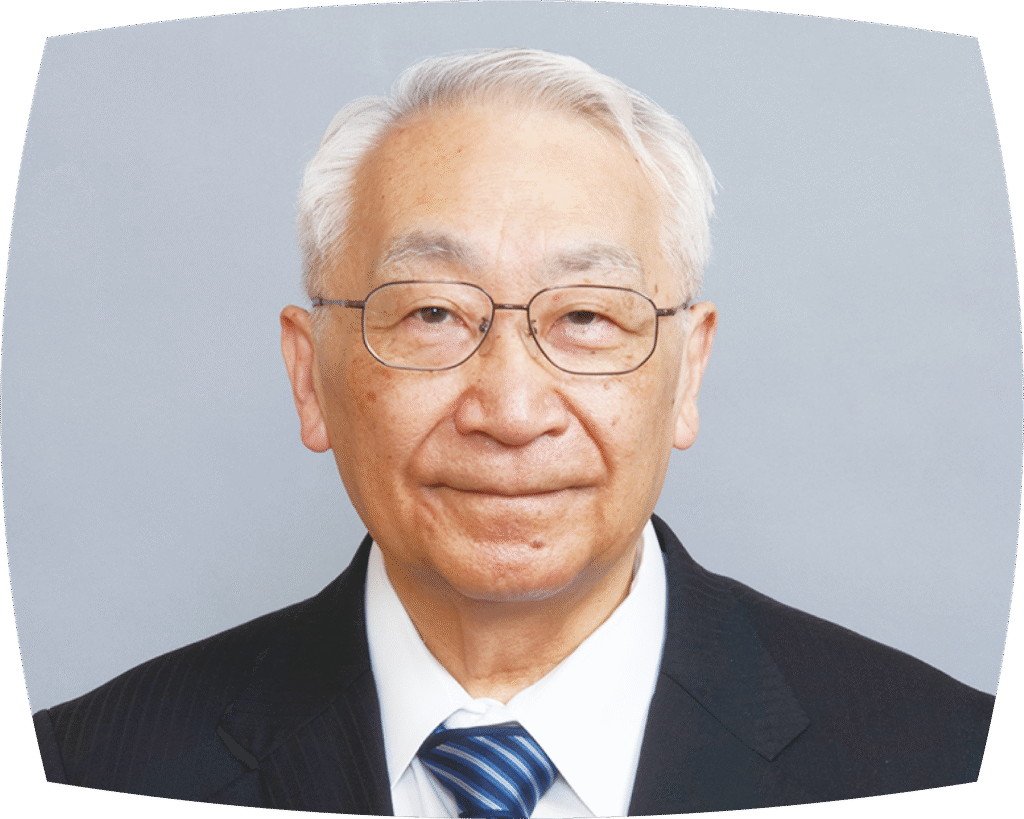
公益社団法人日本医師会副会長
当法人理事
茂松茂人
Shigematsu Shigeto
…………………………………………
シニア期における病気の早期発見とその対応は必須です。気軽に相談できる、かかりつけ医を必ず持っていただくことを強くお勧めします。継続的な視点で関わっていることから、過去の健康状態から未来への予測を含めて最適なアドバイスができる唯一の存在だからです。例えばシニア期以降いくつもの病気を併発した場合、必要な専門的な医療への紹介を含めて、かかりつけ医の役割が必要になります。もうひとつ大切なことは、健康に不安を感じた時、職場にそのことを共有できる理解のある環境があるかという点です。守らなければならない大切な自分の健康。いつまでも生きがいを享受できるために。

公益社団法人日本歯科医師会専務理事
当法人理事
伊藤智加
Ito Tomoka
…………………………………………
歯科疾病は自己治癒はありません。そのため、早期発見・早期治療が重要となります。歯と口の健康は全身の健康に大きく影響します。そのことから、歯科健診による早期発見は国民の健康増進および健康寿命の延伸には欠かせないものです。口腔機能の衰えは「食べる」という機能の低下だけではなく、心身の機能低下につながる負の連鎖とまでいわれます。いわゆるオーラルフレイルを予防することにより、フレイルそして要介護状態へのドミノ倒しを止めることができるかもしれません。若い頃よりかかりつけ歯科医を持ち、日頃から健診を受けて口腔健康管理を行うことが大切です。

公益社団法人日本薬剤師会副会長
当法人理事
原口亨
Haraguchi Toru
…………………………………………
60歳は人生の節目であると同時に、まだまだ社会や職場で活躍できる大切な世代です。だからこそ健康と仕事の両立が重要になります。薬剤師はお薬の安全な使い方を支えるだけでなく、生活習慣全般についても気軽に相談できる存在です。複数のお薬を使う場合には飲み合わせを確認し、副作用を防ぐサポートを行い、必要に応じて医師へつなぐ役割も担います。また職場に健康への理解が広がることで、安心して働き続けられる環境づくりにもつながります。私たち薬剤師は、地域と職場の両面から皆さまがいきいきと過ごし、生きがいを持って働けるよう、60歳からの健康経営を応援しています。
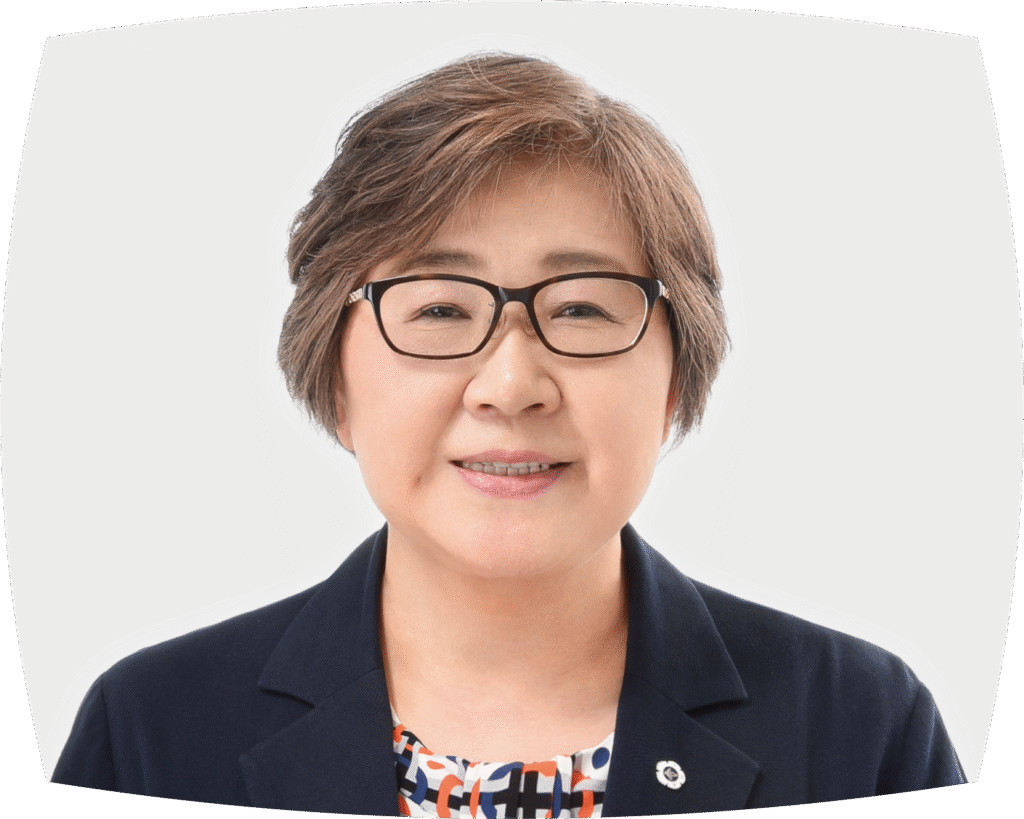
公益社団法人日本看護協会副会長
当法人理事
勝又浜子
Katsumata Hamako
…………………………………………
看護職員は病院や診療所などの医療機関に勤務するだけではありません。地域の保健所や保健センター、また一般企業に勤務して、勤務と治療の両立支援、労働者がより健康になるための保健指導、労働環境の改善などを行っています。少子化の中、60歳を超えてからも社会に貢献することは重要です。私たち看護職員はそんな人々のサポートをこれからも行っていきたいと考えています。私たち看護職員も「プラチナナース」といって、シニア以降も社会に貢献し続けることを希望する方が増えています。

公益社団法人日本栄養士会代表理事・副会長
当法人理事
塚原丘美
Tsukahara Takayoshi
…………………………………………
私たちの身体は、これまでに食べてきた栄養素によってつくられています。また、その身体を成す筋肉や骨、血液、内臓などは、常にダイナミックに入れ替わっています。その材料となるのが、毎日の食事から摂る栄養素です。だからこそ “まとめて” ではなく、“毎日” 補給することが大切です。人生100年時代、60歳からの健康づくりは、働くこと、学ぶこと、地域や社会とつながり続けるための大切な基盤です。60歳から後期高齢者になるまでは、主食・主菜・副菜をそろえ、肉や魚、野菜、乳製品など、さまざまな食品をバランスよく食べ、あわせて身体をよく動かすことが重要です。一方、後期高齢者を迎えたら、最も大切なのは「体重を落とさないこと」です。食事量を減らさず、無理な制限をせず、毎日きちんと食べることが、筋力や活力を守ります。年齢に応じて “食べ方” を見直し、食べる力を支えることが、60歳からの健康経営の第一歩です。

名鉄病院院長
名古屋大学名誉教授
日本老年学会理事
当法人理事
葛谷雅文
Kuzuya Masafumi
…………………………………………
50代以降、年齢とともに新たな病気の発症やそれまで抱えた病気の重症化や外傷(ケガ)も増えていきます。また、老化は確実に進行していきます。そのなかで、リスクを知って、検査やチェックを怠らず早い対応をとれるかどうかは非常に大切です。人生の後半を豊かな時間として過ごすためにも健康をみんなで守っていきましょう。そのためには、職場の応援、サポートこそ大切です。ヒトの健康は連続的なものであり、残念ながら老化は20〜30歳代から既に始まっており、シニア社員時代、さらに退職後の健康もその時々だけではなく、その前から対策を行っていく必要があります。今後の長寿就労社会を見据え、若いときから健診や必要な健康対策を取り入れ、人生の後半を豊かな時間として過ごすためにも健康をみんなで守っていきましょう。
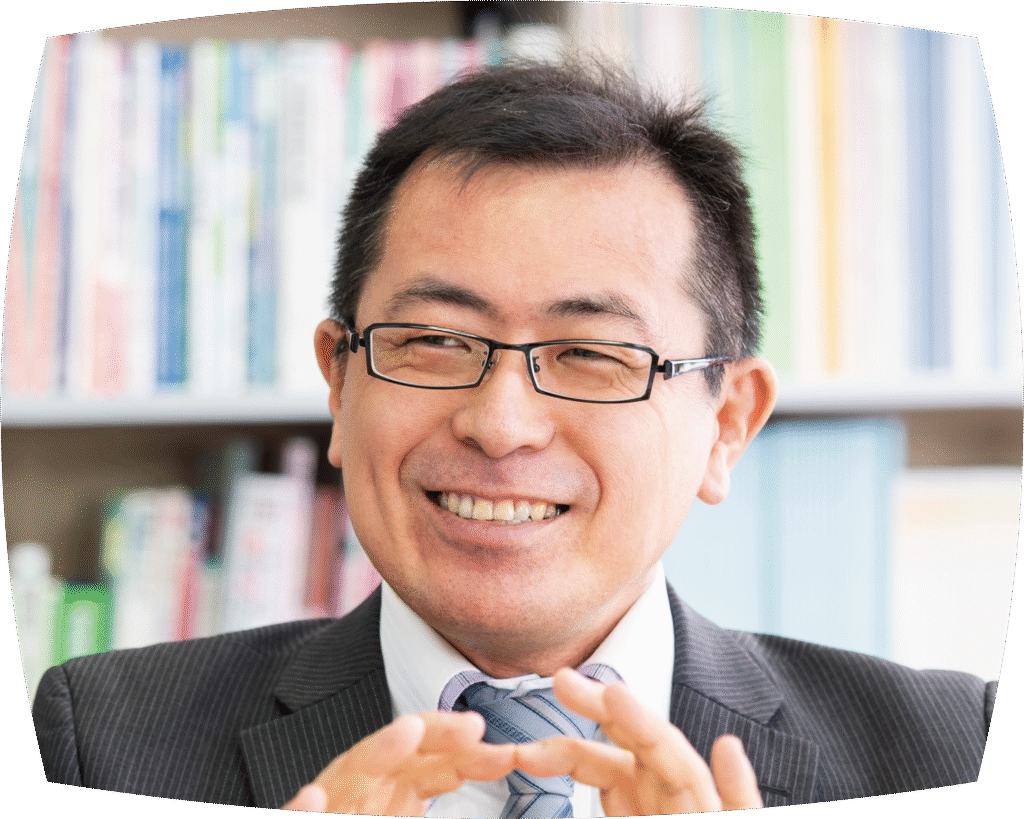
東京大学高齢社会総合研究機構機構長
未来ビジョン研究センター教授
当法人理事
飯島勝矢
Iijima Katsuya
…………………………………………
人生100年時代と言われるなかで、わが国は生きがいも持ち合わせた健康長寿を目指しております。「フレイル」は多面的(身体的・心理的・社会的)な要素を含みながら負の連鎖で自立度が低下しやすくなります。かつ高齢期からすべてが始まるのではなく、思っている以上に早い段階から始まってしまっていますが、まだ可逆性もある状態です。セカンドライフのさまざまな輝き方が注目されているなかで、自身の充実した生活を維持するためにも、そして元気な日本を再び創り出すためにも、企業や職域でも推進しながら、現役の頃からフレイル予防の重要点を知っておくべきでしょう。まさに、フレイル予防は地域づくりそものであり、また国家戦略の要でもあります。
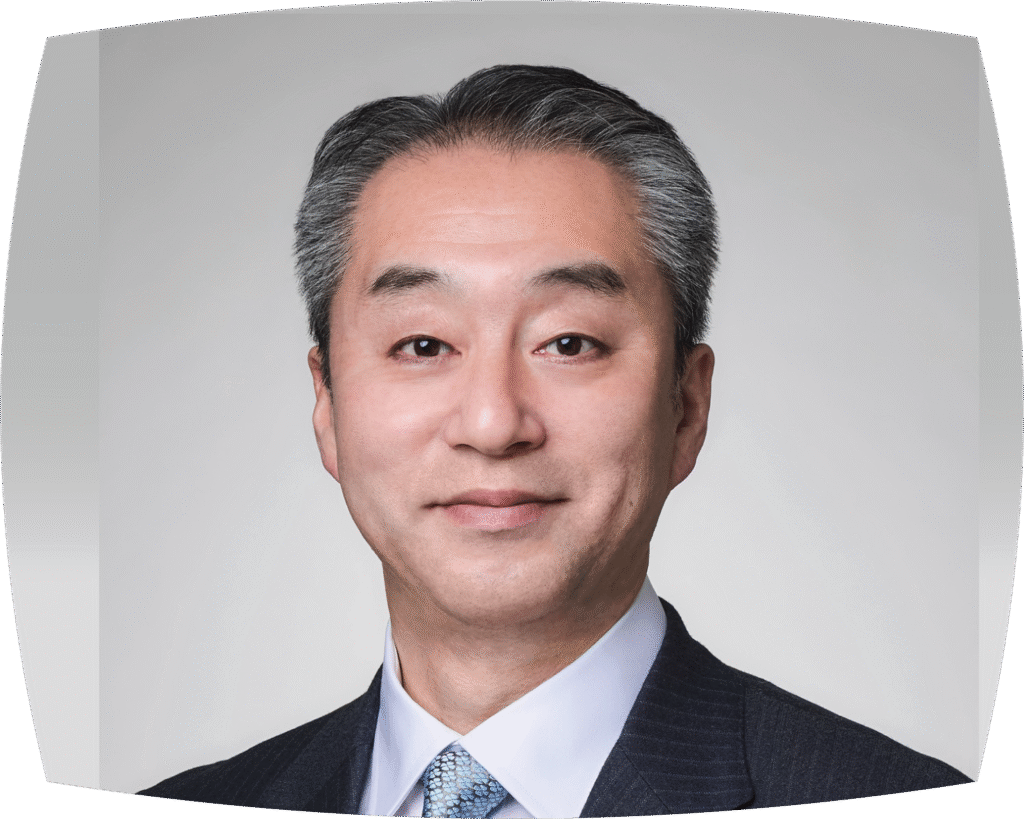
慶應義塾大学医学部
百寿総合研究センター教授
新井康道
Arai Yasumichi
…………………………………………
社会経済的発展や医療技術の進歩の恩恵を受け、私たちはこの100年でかつてない長寿を手に入れました。一方で、認知症やフレイル、骨関節疾患など加齢に伴う疾患が増え、介護が必要となるご高齢の方も増えています。慶應義塾大学医学部は、30年以上にわたって百寿者、超高齢者(85歳以上)の研究を進め、医学や遺伝学、栄養学、社会心理学など幅広い領域から健康長寿のメカニズムの解明に取り組んでいます。研究の結果、百寿者は若いころから肥満や糖尿病が少なく、高齢になってからも動脈硬化を起こしにくいことが明らかになってきました。こうした知見は、40代・50代の現役世代の皆さまにこそ参考にしていただきたい内容です。一人ひとりの方の健康長寿実現はもちろん、“誰もが健康で長生きを喜べる社会” を目指して取り組みを進めてまいります。
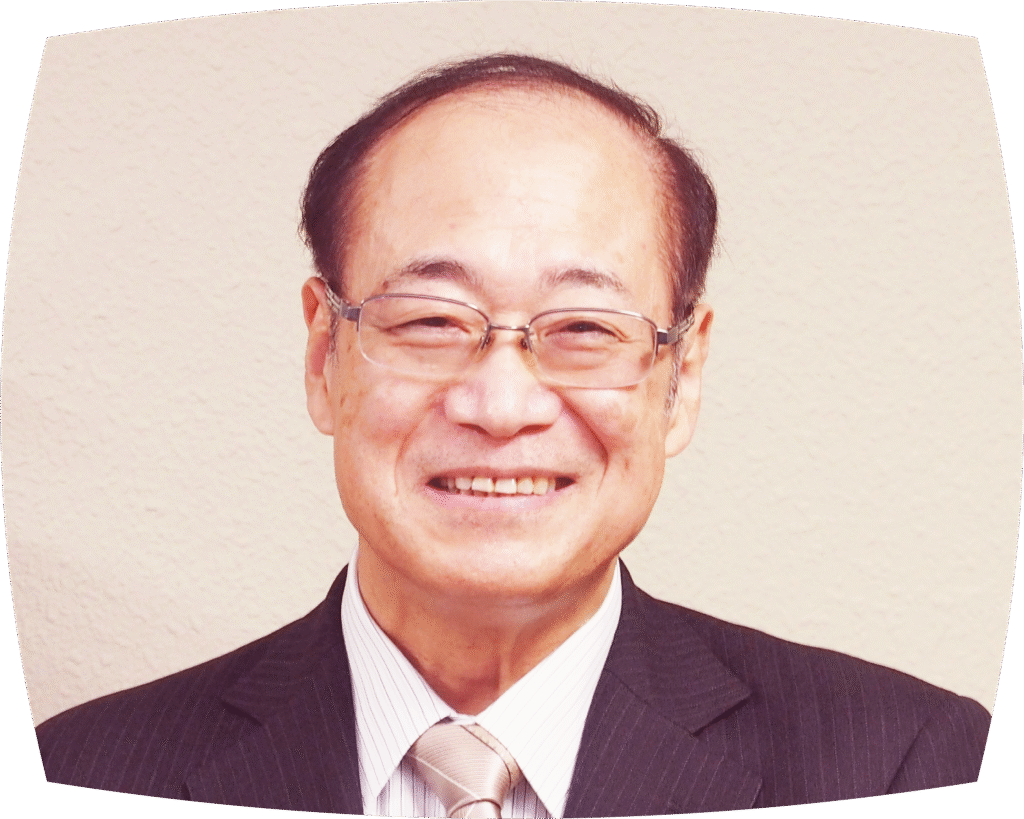
鳥取大学医学部保健学科
認知症予防学講座(寄附講座)教授
当法人理事
浦上克哉
Urakami Katsuya
…………………………………………
さまざまなシーンで「認知症予防に効果あり!」という謳い文句を見聞きしますが、科学的に信頼性の高い予防法は、まだ限られたものであるのが現実です。しかし、世界有数の最新研究では認知症を引き起こす14の要因がすでに特定されていて、これらを乗り越えることで最大45%の予防効果を得られることが明らかになっています。「薬に頼るしかない」「早期発見は早期絶望」「親が認知症だから自分もなるしかない」などと悲観して諦める必要はまったくありません。科学的で正しいアプローチのもと、今からでもリスク因子を管理すれば、死ぬまで元気な脳を維持できる時代に来ています。私の大学のある鳥取県認知症ポータルサイトでは「とっとり方式 認知症予防プログラム」をご紹介しています。認知症進行のスピードは環境に左右されます。周囲の理解とサポートがあり、安心して暮らしている人は進行が遅く、逆に怒られたりするなど不安の多い環境にいると、早く進行します。また初期段階で治療をはじめれば、進行をゆるやかにすることができます。特に認知症の一歩手前の状態である軽度認知障害(MCI)の段階での取り組み次第では認知症の発症を遅らせる、場合によっては健康な状態に回復することも可能です。そうした意味で、早い時期から、すべての人が認知症について正しく学び、理解していただくことが重要です。
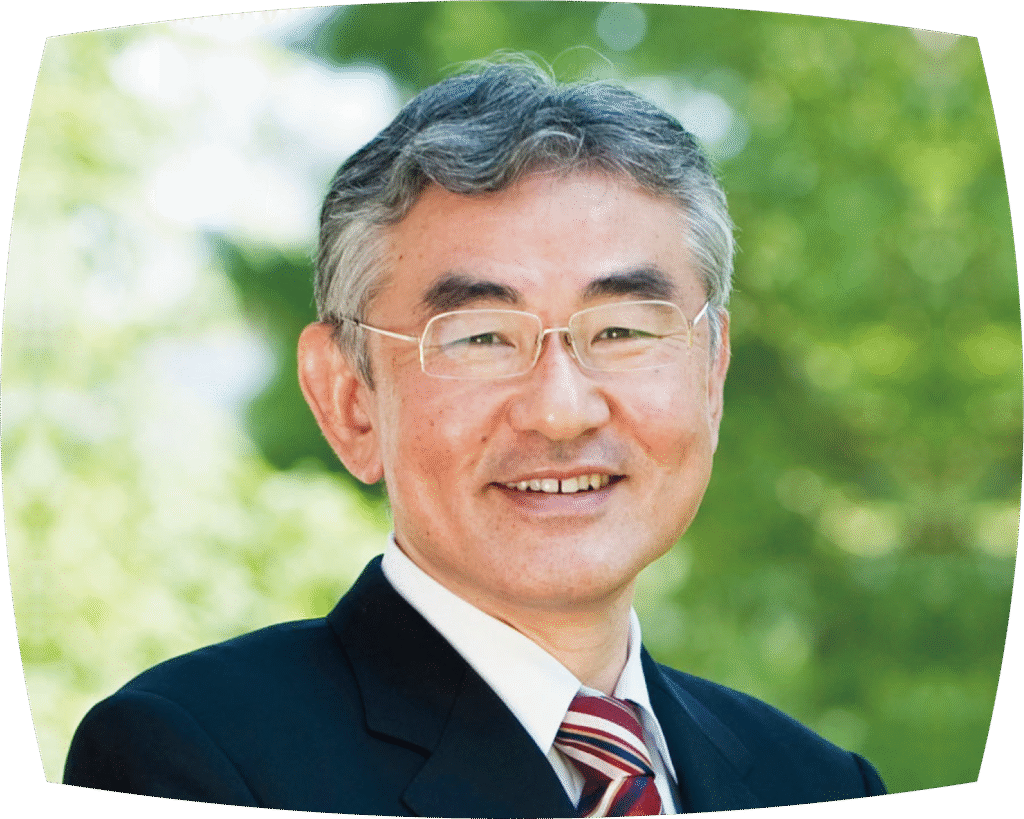
東京慈恵会医科大学客員教授
東京都立大学名誉教授
日本老年精神医学会理事
日本認知症ケア学会理事(前・理事長)
当法人理事
繁田雅弘
Shigeta Masahiro
…………………………………………
認知症も種類はさまざまです。認知症の治療を受けながら、働いている方もおられます。認知症の種別による経過の違いなど、現代人は正しい認知症の知識を身につける必要があるでしょう。また、健康寿命・就労寿命の延伸を目指すシニア就労者支援に加え、認知症とともに働く人の支援も求められる時代です。それは企業のためだけでなく、働く一人ひとりの幸福を支えます。病気の治療を受けながら働く人を支える企業文化は、誰もが安心して働ける職場づくりに直結します。企業の未来を力強く支える取り組みになります。
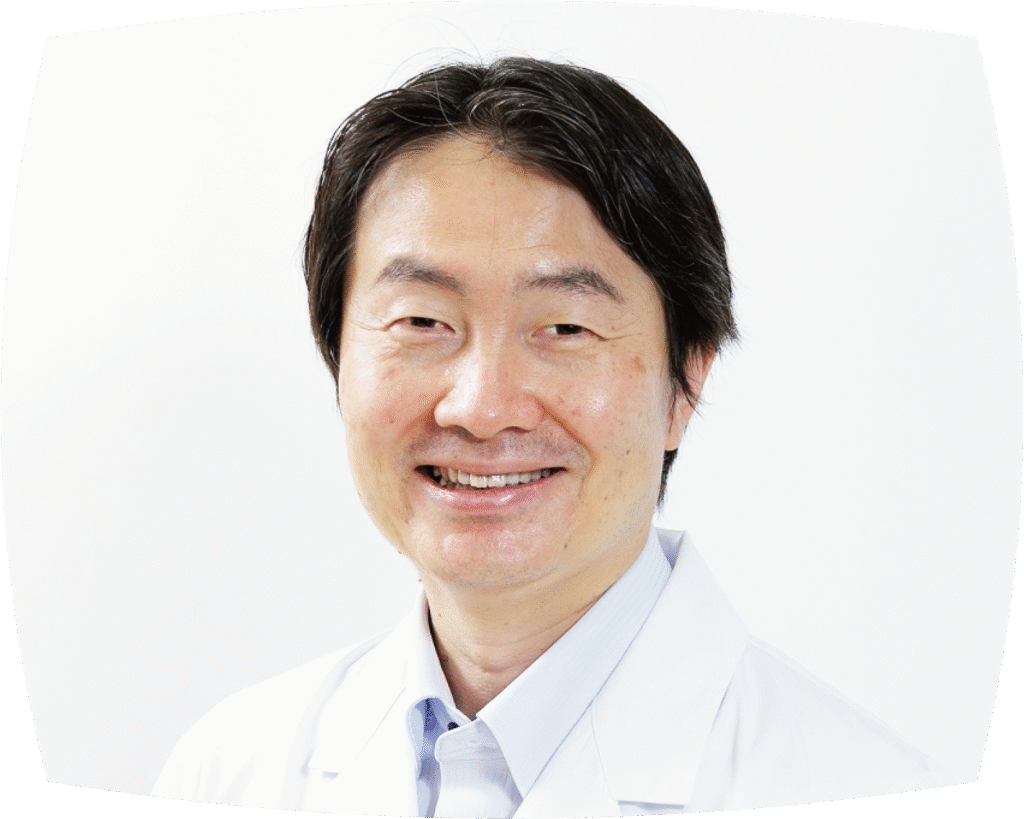
京都府立医科大学精神病態学講座教授
成本迅
Narumoto Jin
…………………………………………
職域での健康経営は、身体の健康だけでなく、心の健康や認知機能の維持にも目を向けることが重要です。近年、軽度認知障害(MCI)や認知症は誰もが直面しうる課題となり、早期の気づきと支援が、本人の生活の質や職場での活躍を支えます。また、ストレスや孤立感などメンタルヘルスの不調は、認知機能にも影響することが知られています。職場で互いに声をかけ合い、予防や相談の体制を整えることは、シニア世代のみならず、すべての働き手にとって安心できる環境につながります。「60歳からの健康経営」を共に進め、心身ともに健やかに働ける社会を実現しましょう。
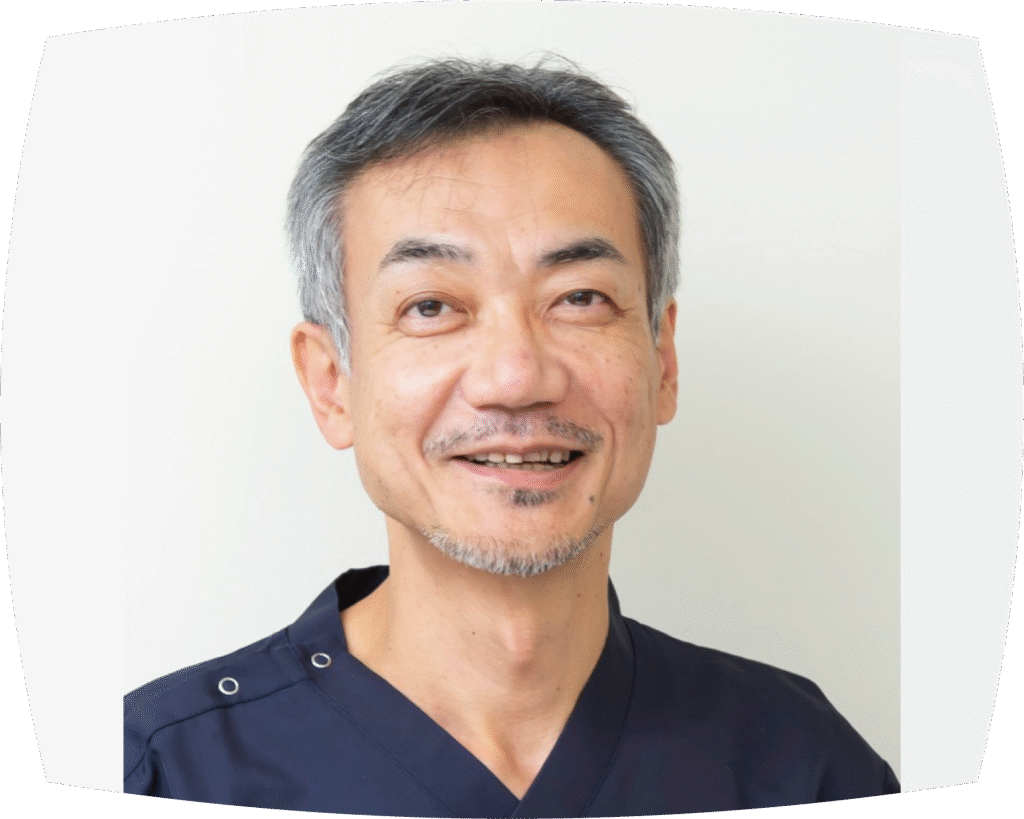
日本歯科大学教授
日本老年歯科医学会副理事長
当法人理事
菊谷武
Kikutani Takeshi
…………………………………………
「食べることは生きること」という言葉をよく耳にします。ただし、この「生きる」という言葉が、単に生物学的な生命を表しているだけではなく、その人の人生であったりや、生活であったりするなどの意味を含んでいる言葉であることは、言うまでもありません。だからこそ、食べることはその人間の尊厳を守り、その人を取り巻く人すべて人の喜びにつながるのです。しかし、食べる機能が衰えると、食事が楽しめない、会話が楽しめないといったことから、家に閉じこもりがちになったり、生活そのものを楽しむことができなくなります。できることならば機能を維持したいと思うのは、誰もが一致しているところでしょう。60歳からの健康経営では、この食べる機能を早い時期から守っていくことを一つの目標としています。
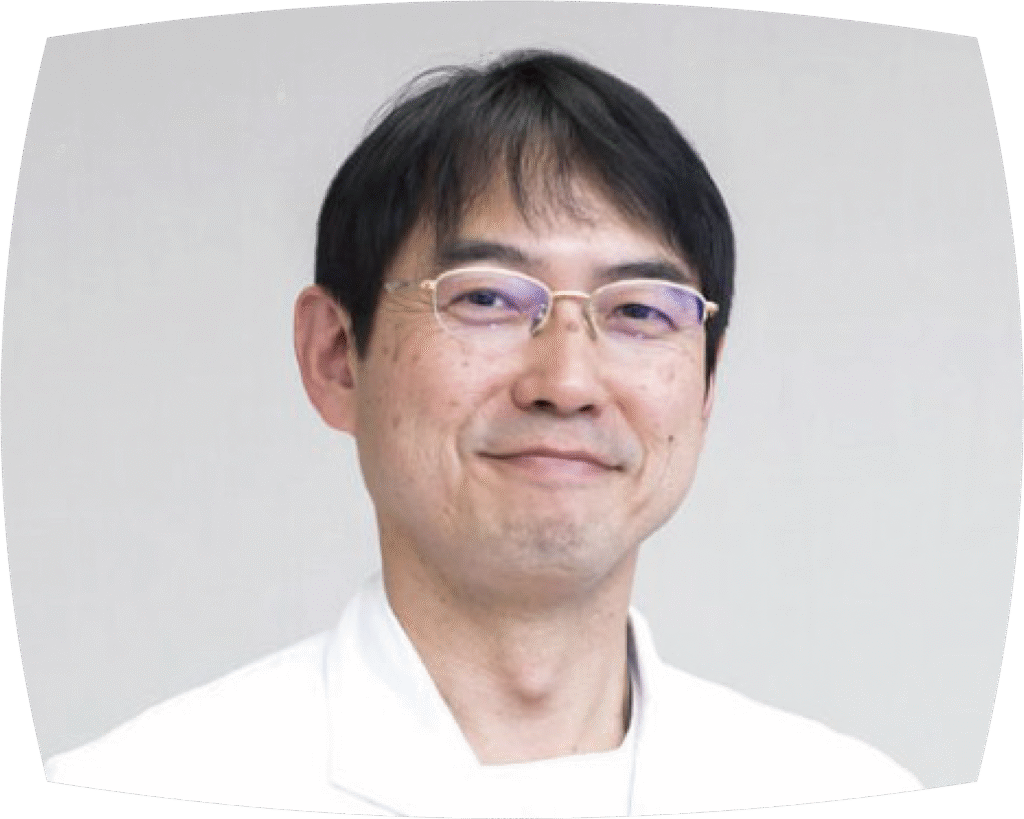
九州大学大学院歯学研究院
高齢者歯科学全身管理歯科学分野教授
当法人理事
柏﨑晴彦
Kashiwazaki Haruhiko
…………………………………………
近年,口腔の健康は全身の健康維持にも密接に関わることが明らかになっています。口腔内は多くの細菌が常在する環境であり、歯周病やう蝕などの口腔疾患は、局所的な問題にとどまらず、全身の炎症や感染症のリスク因子となりえます。たとえば、糖尿病と歯周病は相互に悪影響を及ぼすことがわかっています。さらには、心血管疾患、肺炎、妊婦の早産や低出生体重児のリスク増加などにも口腔疾患が関連するといった報告があります。このように、口腔の健康は全身の健康と深く結びついていることから、職場での健康づくりにおいても日常的な口腔ケアや歯科受診が大切になります。

日本大学歯学部歯学科感染症免疫学教授
当法人理事
今井健一
Imai Kenichi
…………………………………………
お口は、食べ物の入口であると同時に、多くの細菌やウィルスの入口でもあります。50代で肺炎で亡くなる方の25%が、60代では50%が誤嚥性肺炎によるものであり、その原因は口腔の細菌です。被災時の二次被害で亡くなったケースの多くも、口腔ケア(口腔衛生管理)ができなかったことによる誤嚥性肺炎です。また、40代以降の約8割は、歯周病に罹患しています。歯周病菌は、さまざまな口腔細菌やウィルスと連携することで、誤嚥性肺炎を重症化させます。歯周病菌はさらに、新型コロナ感染症やインフルエンザ、そして世界死因第3位のCOPDの悪化にも関わっています。口腔ケアは、高齢者に限らず全ての世代の方にとって、呼吸器疾患を予防し、健康でいきいきと生活するために必須なのです。
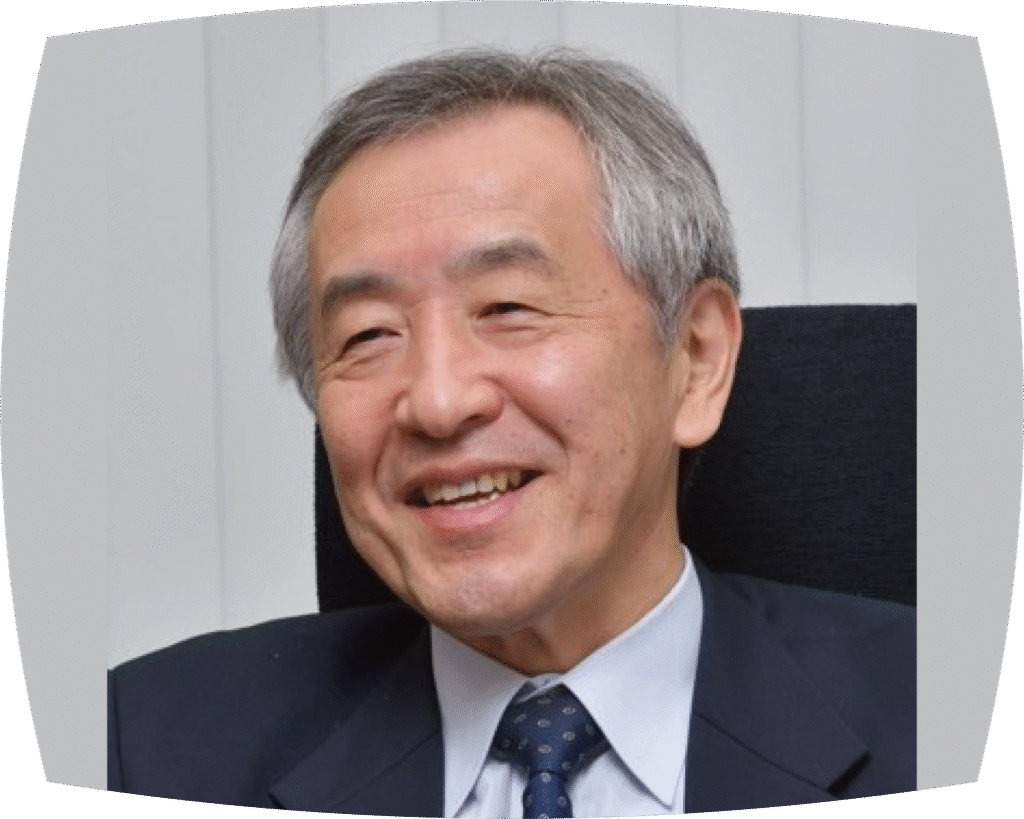
公益社団法人国民健康保険中央会
理事長
原勝則
Hara Katsunori
…………………………………………
人生100年時代、地域住民の皆さまには、大切な後半人生を少しでも健康で過ごせるために、運動や栄養、休息などご自身の健康管理に一層取り組んでいただき、病気が疑われるときには、重篤な状態にならないうちに早期に受診を心がけていただきたいと思います。そのためにも、さまざまな機会を通じて、健康についての知識を学び、少しでも健康を損なうリスクを避けて過ごしていただきたいと思います。私たち、国民健康保険団体連合会は、市町村や後期高齢者医療広域連合等の保険者とともに、データを活用しながら、皆様方お一人おひとりの健康づくりを全力で支援してまいります。

全国健康保険協会(協会けんぽ)理事
川又竹男
Kawamata Takeo
…………………………………………
いつまでも健康で生活し、働き続けることのできる社会を目指して、協会けんぽ(全国健康保険協会)では、生活習慣病予防健診、特定保健指導等を推進するほか、事業主や経済団体、業界団体とも連携協力しながら、「コラボヘルス」の取り組みを進めています。「健康宣言」事業所の数は、全国で10万を超えており、職場全体での健康づくりや、従業員の健康の保持・増進を図るための取り組みについて、協会けんぽは全力でサポートしています。

国際医療福祉大学大学院特任教授
大林尚
Obayashi Tsukasa
……………………………………………………………
2025年の5月、92歳の誕生日を迎えてからほどなくして父が生涯を閉じた。その半年ほど前に入居した老人ホームの自室のベッドで、眠っているあいだに亡くなった。死因は老衰。この数年、足腰を傷めたり胃がんの手術を受けたりと、必ずしも体調万全とは言えなかったが、それでも私たち家族に大きな負担をかけることなく終末期をすごした。
いわゆる昭和一けた世代の父は、ごく一般的なサラリーマン人生を歩んだ。高度成長期は会社の中堅どころとして猛烈に働いていた。当時ほとんどの男がそうであったように、ショートピースをぷかぷか吸っていた(のちにセブンスター、そしてマイルドセブンへと銘柄を変えたが)。
一方で、ふだんから速足でよく歩き、好き嫌いなく何でもよく食べた。60歳定年の数年前に勤め先を退職し、請われて同業の会社に再就職し、フルタイムではないが70歳まで働いた。その頃には煙草もやめていた。引退後は謡曲の稽古に精を出し、それが高じてお能の舞台に欠かせない大太鼓を叩いたり、能面を打ったりもした。
大きな病気はほとんどしなかったが、前述のように89歳のときに胃がんがみつかり、専門医の診断を受けて内視鏡手術で病巣を摘出し、寛解した。執刀医は「今後5年間、がんで亡くなることはないでしょう」と太鼓判を押した。
永年親しくしている医師に父の最期の様子を聞かれ、ありのままに話したら「お父上は理想の死に方ですよ」と言われた。そして「あなたもその血を受け継いでいるのだから、長生きして自然に死ななきゃだめですよ」と付け加えた。
会社勤めの身にとって定年後をどう生きるか。さまざまな選択肢があるとはいえ、したいことを存分にする要諦はやはり健康人でありつづけることに尽きる。先立つものは不可欠だが、心身に不調を抱えていてはその使途をしたいことに振り向けるのがむずかしくなる。もっとも適度な運動、心地よい睡眠、バランスの取れた食事——と、健康を保つ要素をまっとうしつづけるのは、容易ではなかろう。強い意志の継続が試される局面だ。筆者もその例外ではない。
悔いのない最期を迎えるために、そのような人間の弱さを克服しようとする努力が決定的に重要なのだ。「60歳からの健康経営」は、そのよき伴奏者のひとりとなろう。
父は最晩年、時折「ぼくはこんなに長生きするとは思っていなかった」と、口にすることがあった。私もそんな気持ちになれるだろうか。